トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 環境ポータルサイト ecoco「エココ」 > 環境問題キーワード解説 > 第6回 サーキュラーエコノミー・循環経済
0007
更新日:2022年10月07日 11時34分
近年、カーボンニュートラル(脱炭素社会)の実現やライフサイクル全般での資源循環に関する取り組み等が急速に進展しています。
環境問題への配慮が不十分な時代は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済活動が行われていました。大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、健全な物質循環を阻害するほか、気候変動問題、天然資源の枯渇、大規模な資源採取による生物多様性の破壊など様々な環境問題にも密接に関係しています。
このことから、これまでの経済活動の中では廃棄されてきたような製品や原材料などを資源として捉えて活用し、持続可能な状態で循環させる考え方が主流になっています。それが「サーキュラーエコノミー(循環経済)」と言われています。
このサーキュラーエコノミーという用語は、EUが2015年12月に政策パッケージを公表したことで世界的に広まった概念で、和訳して「循環経済」と呼びます。
SDGsや環境問題に関するニュースの際などに耳にする機会が増えて来ました。
今回は、このサーキュラーエコノミー・循環経済の意味を分かり易く解説し、サーキュラーエコノミー・循環経済に向けた動向を紹介します。
サーキュラーエコノミー(Circular Economy)・循環経済は、従来の「リデュース・リユース・リサイクル(3R)」の取り組みに加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す経済活動であり、資源・製品の価値の最大化、資源消費の最小化、廃棄物の発生抑止等を目指すものです。
このサーキュラーエコノミー・循環経済に対して、従来の大量生産・大量消費型の経済システムでは、地球の資源を採って物を作り、使い、最終的に廃棄するという一方向のみの流れで直線的でしたのでリニアエコノミー(Linear Economy)と呼んでいます。
この廃棄を前提としているリニアエコノミーと異なり、サーキュラーエコノミーは最初から廃棄物を発生させないという考えが軸になっています。
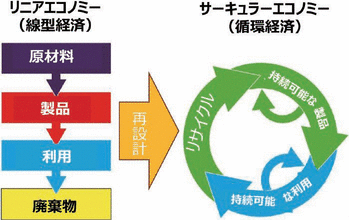
出典:令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書(環境省)
イギリスに本拠を置く国際的なサーキュラーエコノミー推進機関として有名なエレン・マッカーサー財団は、サーキュラーエコノミーの3原則として、次を掲げています。
先頃、令和4年9月に中央環境審議会循環型社会部会は、「2050年の循環型社会に向けて (8585キロバイト)
(8585キロバイト) 」と題する報告書を公表し、サーキュラーエコノミーへの移行を加速するため、2050年を見据えて目指すべき循環経済の方向性と2030年に向けた施策の方向性を、循環経済工程表として取りまとめています。その中で、次のように述べられています。
」と題する報告書を公表し、サーキュラーエコノミーへの移行を加速するため、2050年を見据えて目指すべき循環経済の方向性と2030年に向けた施策の方向性を、循環経済工程表として取りまとめています。その中で、次のように述べられています。
 (2310キロバイト)
(2310キロバイト) )を掲げている。
)を掲げている。サーキュラーエコノミー・循環経済への移行がなぜ必要なのか。それは、現在のリニアエコノミーは環境・社会の両面から考えて持続可能な経済モデルではないことが明らかになってきているためです。
これからは、製品を生産する段階から消費者が利用・廃棄する段階で終わるのではなく、廃棄されていた製品や原材料などを資源と捉えてメンテナンス、リユース、リサイクルに至る全体のサイクルが循環的に行われるように取り組むサーキュラーエコノミー・循環経済が基本となります。
また、サーキュラーエコノミー・循環経済への移行は、企業の事業活動の持続可能性を高めるため、ポストコロナ時代における新たな競争力の源泉となる可能性を秘めており、現に新たなビジネスモデルの台頭が国内外で進んでいます。サーキュラーエコノミー・循環経済を競争力の源泉とし、限りある資源の効率的な利用等により世界で約500兆円の経済効果があると言われている成長市場(出典:Accenture Strategy 2015)の獲得を目指すことになります。
藤田 八暉
久留米市環境審議会会長
久留米大学名誉教授